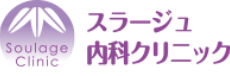KIDNEY
腎臓内科・むくみ外来
腎臓病とは

たんぱく尿、血尿、むくみ(浮腫)、高血圧、尿量の変化など
腎臓は、そらまめのような形をした握りこぶしくらいの大きさの臓器で、腰のあたりに左右対称に2個あります。腎臓病は、この内臓が何らかの原因で障害を受ける病気です。症状としてたんぱく尿、血尿、むくみ(浮腫)、高血圧、尿量の変化などがみられます。腎臓病が著しく進行すると、老廃物が排出できず尿毒症という深刻な状況になります。
これらの症状は必ずしも出現するとは限らず、特に軽度のうちは顕著ではないことが多く、見過ごされがちです。また、慢性で徐々に進行した場合には、自覚症状に乏しいということもしばしばあり、そのために発見が遅れ、気がついたときには腎不全が進行してすでに慢性腎不全の状態、透析導入の一歩手前というケースも珍しくありません。
-
たんぱく尿
腎臓に糸球体という場所があります。これは毛細血管の塊で血液から老廃物等を濾過して尿の大元(原尿)を作る場所です。基本的にたんぱくはここで濾過されません。あるとしてもごくわずかの量のみです。明らかなたんぱく尿が認められる場合には、腎臓の病気がかくれている可能性があります。
-
血尿
赤血球は健康な人でも尿中に排泄されていますが、尿中にもれる量はほとんどありません。
しかし、腎臓の糸球体から尿管、膀胱までになんらかの障害(炎症、石や腫瘍など)があると、尿の中に赤血球が混じることがあります。
肉眼ではわからない顕微鏡で見える程度の顕微鏡的血尿から、茶褐色尿~鮮血の肉眼的血尿までさまざまな程度で観察されます。 -
むくみ(浮腫)
むくみの原因はいろいろあります。その中で腎臓が原因のものは主に2種類あります。一つは腎臓から水分や塩分の排泄が十分に行われない場合、もう一つは尿へたくさんたんぱく質が出てしまい血液中のたんぱく質が少なくなって血液が薄くなり、血管外に水分が漏れ出てしまう場合です。
特に腎臓の機能が低下すると体内の余分な水分や塩分が十分に排泄されず、水分量のコントロールができなくなります。すると、体にたまった余分な水分はむくみとして観察されるのです。
むくみは腎臓の機能の低下以外の原因(たとえば心臓の機能の低下など)でも起こりうるので、しっかり原因を突き止めたうえで治療をすることが大切です。 -
尿毒症
腎臓の働きが低下し、尿から排泄できなくなった毒素や不要な老廃物が血液中に溜まった状態です。尿毒症の患者さんは、
- 全身の倦怠感(だるさ)
- 疲労感
- 食欲の低下
- 嘔気や嘔吐(気持ちが悪く吐き気がすること)
- 高血圧
- 睡眠障害
- 呼吸苦
などのさまざまな症状を示します。
また、腎臓の働きが低下するとエリスロポエチンという赤血球をつくるために大切なホルモンが低下し、赤血球がつくられなくなるために「貧血」などがみられることもあります。
尿毒症の状態を放置すると、いずれは昏睡(意識がもうろうとした状態)となるなど、生命に関わる深刻な状態に陥ります。 -
たんぱく尿
腎臓は塩分の排泄や、内分泌機能のレニン系を介した血圧を調節する機能をはじめとして、血圧コントロールにおいて重要な役割を担っています。このため、腎臓の機能が低下してくると高血圧を来たしやすくなります。
高血圧は、頭痛や肩こり、吐き気などの症状を引き起こします。 -
血尿
腎臓の機能が低下してくると尿を濃縮できなくなり、しばしば尿量が多め(多尿)になるということもあります。
しかし、腎臓病がさらにすすむと、尿をつくることができなくなるため、最終的には尿量が減ってきます(乏尿)。
腎臓の機能がなくなり、まったく腎臓が働かなくなると、尿はつくられなくなり、尿量は0mlとなります(無尿)。
そもそも腎臓の働きって何?

腎臓は血液をろ過して尿を作るだけではなく、体老廃物を排除したり、血圧を調整するといった重要な働きをしています。
主な腎臓の役割を見ていきましょう。
ROLE1老廃物を体から排出する。
腎臓は血液を濾過して(ふるいにかけてこして)老廃物を尿として体の外へ追い出してくれます。また、一旦輩出したものの中にある体に必要なものは再吸収し、体内に留める働きをしています。腎臓の働きが悪くなると尿が出なくなり、老廃物や毒素が体に蓄積し尿毒症になります。
ROLE2血圧を調整する。
腎臓は、塩分と水分の排出量をコントロールすることによって血圧を調整しています。腎臓は塩分や水分の排出量を調整することができます。血圧が高いときは、塩分と水分の排出量を増加させることで血圧を下げ、血圧が低いときは、塩分と水分の排出量を減少させることで血圧を上げます。また、腎臓は血圧を維持するホルモンを分泌し、血圧が低いときに血圧を上げます。しかし、腎臓の具合が悪くなると、塩分・水分の排出量の調整が効かなくなったり、ホルモンの分泌が過剰になったりして血圧が高くなります。また、高血圧は腎臓に負担をかけ、腎臓の働きをさらに悪化させることもあります。
ROLE3血液を作るホルモンを産生します。
腎臓は血液(赤血球)を作るホルモン(エリスロポエチン)を産生できる唯一の臓器です。そのため腎臓の働きが悪くなると、このホルモンが出てこなくなってしまい、血液が十分につくられず貧血になることがあります。腎機能が悪くなり、貧血が生じた場合このホルモンを補充(注射)する必要があります。
ROLE4水分・ミネラルのバランスを整えます。
腎臓は体内の水分量(体液量)やミネラルバランスを調節する役割も担っています。腎臓が悪くなると体液量の調節がうまくいかないため、体のむくみにつながります。また、ミネラルのバランスがくずれると、疲れやめまいなど、体にさまざまな不調が現れることがあります。特にカリウムが高くなると、不整脈等が起こるため注意が必要です。
ROLE5骨を強くします。
腎臓は、カルシウムを体内に吸収させるのに必要な活性型ビタミンDをつくっています。これによって腸や腎臓からのカルシウムの吸収を高めることができます。腎臓の働きが悪くなるとこの活性型ビタミンDが低下し、カルシウムが吸収されなくなって骨が弱くなるなどの症状が出てきます。
腎臓病の何が問題なの?
- 01
患者数が多い。
2008年の日本腎臓学会による統計では、日本の成人の8人に1人にあたる、1330万人の方が慢性腎臓病(CKD)患者さんと推測されています。あまり知られていませんが、残念ながら腎臓病はとても身近な病気なのです。
“国民病”とでもいうべき患者数の多さに、厚生労働省をはじめとして公的な機関も積極的に対策に乗りだしています。 - 02
自覚症状が乏しいです。
腎臓は大変頑張り屋の臓器で、徐々に進行した腎不全では腎臓の機能が20%程度になるまで、体に異変や不調が見られることはほとんどありません。
そのため、検査以外で発見されることはなく、自覚症状のないまま放置されがちです。健康診断は定期的に必ず受診しましょう。 - 03
心筋梗塞や脳卒中との
関係が深いです。腎臓病では、血管がダメージを受けることや高血圧・糖尿病など他の病気の影響で動脈硬化が進行しやすくなります。これにより、血液の流れが悪くなり、心筋梗塞や脳卒中を引き起こす可能性が高まります。
スラージュ内科クリニックで出来ること

各種腎臓病の診療ができます。特に、糖尿病等で腎機能が低下した方の腎保護治療に精通しています。腎不全に対する特効薬はないのですが、食事療法や運動療法を基本にアンギオテンシン受容体拮抗剤やカルシウム拮抗薬、各種利尿剤、レニン拮抗薬、スタチン製剤、DPP-IV阻害剤、高尿酸血症など腎保護効果が認められている薬剤を駆使して治療に当たります。
これまでのところ、ほとんどの患者様で安定的な腎保護効果を認めており、今後も腎保護を治療の柱に据えて診療にあたります。
腎不全の治療について
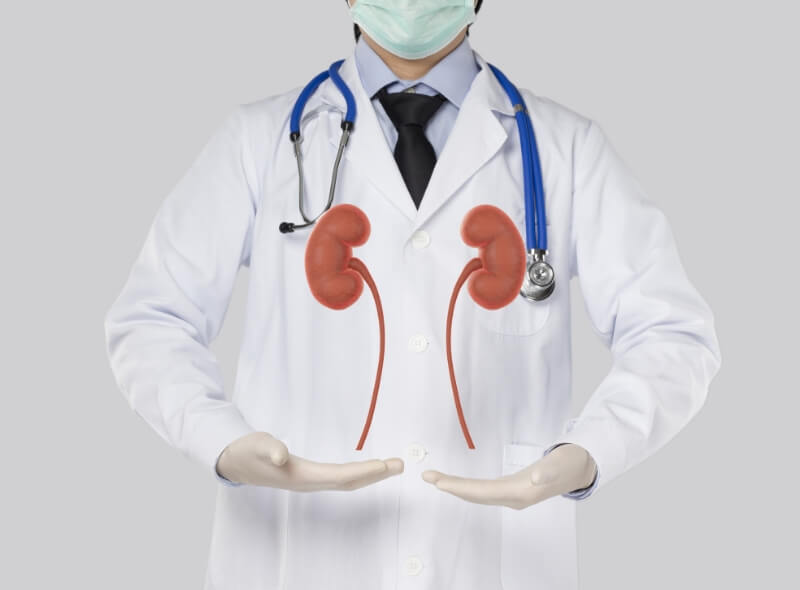
それでも腎不全に陥る方もいらっしゃいます。でもご安心下さい。当院では腹膜透析という治療方法を取ることができます。私どもは同治療にも精通しています。また当院で腎不全に対する「腎臓機能障害身体機能障害申請」を出す資格があり、身体障害申請を行います。医療費用負担軽減のお役に立ちます。
他に血液透析や腎移植という治療方法もありますが、連携医療機関に責任を持ってご紹介いたします。
腹膜透析のご案内

胃、腸、肝臓などおなかの中にある内臓と腹壁というおなかの壁を覆っている膜を腹膜と言います。この腹膜が体を浄化する能力のあることがわかっています。この能力を利用して腎不全の浄化をしようというのが腹膜透析です。いわば「腎臓の替わりを腹膜にさせよう」という考え方です。
1回あたり腹膜透析液1リットルから2リットル程度をおなかの中に入れます。貯留時間は4時間程度でこれを数回繰り返します。最近は寝ている間に自動的に注入と排液をしてくれる装置もあります。注入するためのカテーテルはあらかじめ設置しておきます。
患者さんにしていただくのはこのカテーテルに透析液のチューブをつないで注入と排液をおこなっていただくだけです。非常に簡便な操作です。
腹膜透析のメリット
この治療のメリットはまず体に非常に優しいということです。血液透析は血液を体の外に出していわば強引に血液を浄化するので心臓などに負担がかかる可能性があります。腹膜透析はそれが少ないです。
また通院がつき1、2回と制限が少ないです。血液透析は週3回程度の通院と1回あたり4時間程度の治療時間を要し、生活制限があります。これまでの事例として、腹膜透析患者さんでヨット世界一周した方もいますし、仕事で出張の多い方も仕事をこなしておられます。主婦業や子育てをしっかりこなせておられる方もたくさんいらっしゃいます。